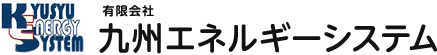蓄電システムのあるくらし
メリット01

突然の停電!でもあわてない。
災害などで突然の停電が発生すると、不安で不便な時間をすごすことに…。停電した時でも、蓄電システムがあれば、安心です。停電時は、大容量の蓄電システムから自動で瞬時にバックアップ。16.6kWh蓄電システムでは標準的な家電の組合せ(約430W)で最大30時間の連続使用が可能です。
メリット02

家計をお助け!電気代節約が可能。
昼間高く、深夜割安になる電力プランにご加入のお宅では、昼間の電力ピーク時に、前日の深夜に蓄えた蓄電システムからの電気を使うことで、電力会社から購入する日中の電力量を抑制することができます。普段と同じ量を使っても昼夜の電気料金の差額の分だけ電気代を節約できます。
メリット03

エネルギーを自給自足する家へ!
太陽光発電システムと蓄電システムを連携させると、電気をより効率的に使えます。昼間は太陽光発電で作った電気でまかない、余った分を蓄電システムに蓄えて夜間使用することで、電気の自給自足が目指せます。長時間の停電が続いてもお天気が良ければ夜間も電気が使えるので、安心です。
蓄電池の仕組み
仕組みについて

一般に、充電することで電気が蓄えられ、繰り返し使える電池を総称して「蓄電池」と呼んでいます。 スマートフォン(スマホ)のバッテリーなどは私たちの暮らしにもっとも身近な蓄電池(充電池)と言えるでしょう。 また、蓄電池は放電後も再充電することで繰り返し使えることから二次電池とも言われています。 下記に示すように蓄電池にもさまざまな種類がありますが、その多くは金属の持つイオン化傾向を利用して酸化還元電位を発生させる「化学電池」と呼ばれるもの。
ふつうの電池(一次電池)は、プラス極とマイナス極にイオン化傾向の異なる金属を置き、その間を水酸化ナトリウムなどの溶液で満たしていますが、使えば放電する一方で充電ができません。 これに対して、蓄電池(二次電池)では、一度放電しきっても、電極に適正な電圧をかけることで内部の化学物質が放電と逆の反応を起こして元の状態に戻ります。 これが蓄電=充電の仕組みです。
種類と特徴

この蓄電池=充電池にもいくつかの種類があります。 代表的なのは自動車に搭載されている鉛蓄電池。 ほかにも、携帯やスマホ、パソコンに電力を供給するリチウムイオン電池、ラジオや懐中電灯などで使われることの多いニッケル水素電池などが代表的です。 下記では、それぞれの特色を解説しています。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 鉛蓄電池 | 特徴 電極に鉛を用いることから鉛蓄電池と呼ばれています。 電圧や容量を大きくできるので、自動車や産業用機器など大電力を必要とする用途に多く用いられます。 反面、電極が劣化しやすく、一度放電しきると、本体の劣化も進みやすいなどの欠点も。 |
| リチウムイオン電池 | 特徴 充電や放電を何度も繰り返したり、継ぎ足して充電したりできる特性があるので携帯やスマホ、パソコンなどに多く用いられています。 最近ではハイブリッドカーや電気自動車の動力源としても採用されています。 充放電特性は優れていますが、満充電の状態、放電しきった状態では劣化しやすいといった特徴もあります。 |
| ニッケル水素電池 | 特徴 一般的なマンガン乾電池、アルカリ乾電池の代替として用いられることが多いのがニッケル水素電池。 その形状、サイズも、単三型、単四型など一般の乾電池と同じ規格で作られています。 ラジオや懐中電灯などに気軽に使えますが、リチウムイオン電池と異なり最後まで放電しきらないうちに充電すると、電池の持ちが悪くなるメモリー効果と呼ばれる特性があります。 |